近頃、街の多くで見かける「文字」が、変化を遂げている。よく見る広告やさらにはテレビの字幕スーパー 等・・・
近年の今の世で変わりつつある「文字」というものを、1つのデザイン関連としてのコラムにして、ここに記そう。
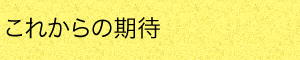
今まで、「写研フォント」について色々と書いてきましたところで、私なりのこれからの「あるべきフォント環境」の提案を。
まず1つ問題があり、実は写研は「ホームページを持っていない」のだ。これは何回聞いても納得できない。まるで自社の情報を世の中に出すのを否定している?ような苦い感触を覚えてしまう。このコラムを読んで、少しでも共感を持ってくれる人がいたら、このコラムを書いて良かったと思いたい。
また、今の時代で活躍する様々な若いデザイナーの中には、「写研フォントって何?」というように、名前も存在も知らない人が多々いるという情報も耳にしたことがある。これを知ったときはさすがに「おいおい・・・」と思ってしまった。
もちろんこのコラムを書いているdesigng.info制作者のtakkaも、あくまでこのサイトは「趣味」として運営しており、その道の専門業ではない、いわゆる「第三者」ではあるが、それでもこのフォントは(個人的にも)元々好きで、インターネット上から様々な情報を集め、自分なりに勉強をし、知識を少しは付けたつもりではある。その「第三者」から言わせてもらえば、やはりDTPやデザイナーなどの業種に携わっている人ほど、今の時代に流れているフォントだけでなく、フォントの世界全般をしっかりと知っていただきたいのだ。そして、周りが同じフォントを使っているから、うちも・・・という一方的な考えだけでなく、相手が読んで読みやすく、単純に「良いフォント」を使うのは基本的なことではないのだろうか?
どのような事柄でもいいので、是非とも写研には、まずホームページを公開し、今の「写研フォント」そのものを知らない人にもアピールして、知識を深めてもらえるような機会を与えてほしい。今の世の中をもっと知ってほしい。少なくとも、写研サイドからしても、いい広告にもなるはずなのに、やはりもったいないのだ。出せるチャンスをわざと出さない、みたいに・・・。
このフォントが使いたいという人は世の中に少なからずいます。年々増えているはずです。
最後に、写研様へ一言。
写研さん、これを読んでいる皆さんは、あなたのフォントがいかにすばらしく、優れた文字であるかをよく知っているのです。独自路線で突き進むよりは、文字という共通の文化を、誰もが使えるように、よりオープンにしていただければと思います。
以上の「伝えたいこと」を書き、このコラムはここまでと・・・。